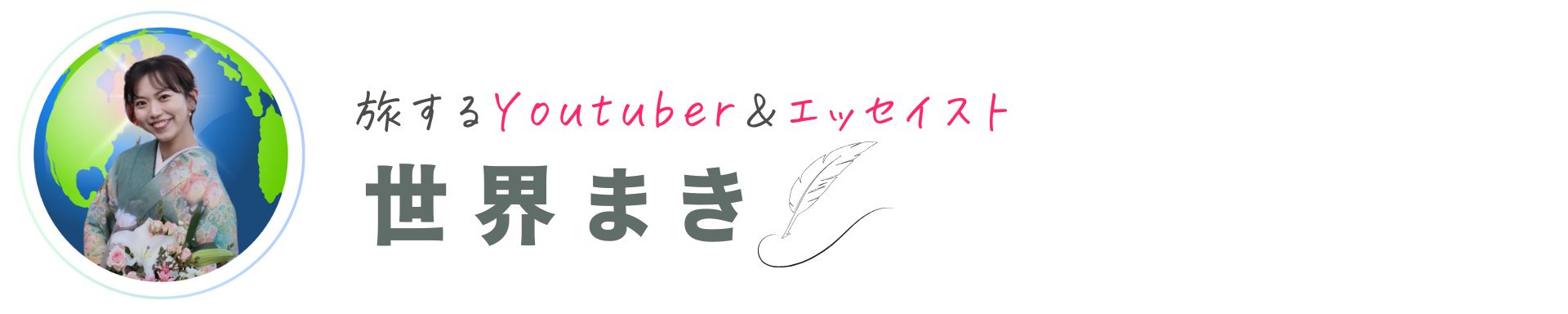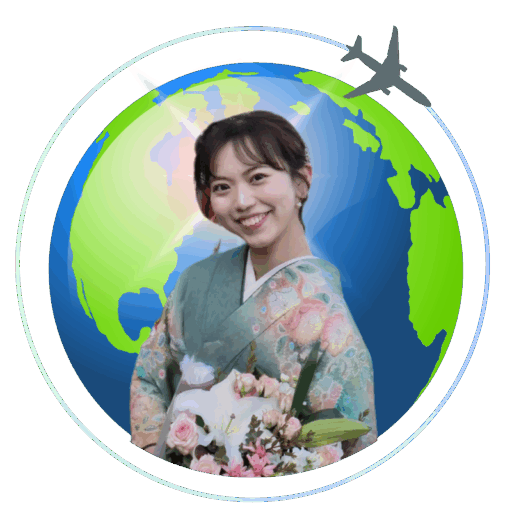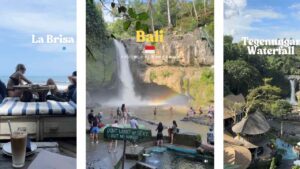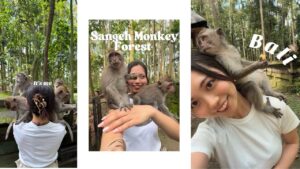こんにちは!
世界一周ひとりバックパッカー旅をしている女子大生の”まき”です!
インドの朝は、祈りで始まる
朝4時、5時。まだ気温もひんやりしている時間帯にも関わらず、
ガンジス川にはたくさんの人が止まっていた。
地元の人はもちろん、インド各地から心身を清めるために
遠いインド各地から来た人々で賑わっていた。
だれも時間に追われることなく、自分のペースで、自然に体を動かしている。
決まった形はなく、各々が自分のやり方で祈りを捨てている様子が、
自由で美しく感じられた。
各自の祈りの形が、この地を「自由な領域」にしていた。
早朝5時半にここを訪れば、太陽が川の水面に線を形成して明らむ光景が、
体をほかほかにしてくれる。
そこで見た火葬場
「お墓のない国、ものがたりのある国」ヒンドゥー教の基本思想「軒生転生」。
そのため、肉体を埋葬するのではなく、火蔽して、道に返していく。
そのこの話の中で「カーストは残ってるの?」と聞いたら
「もちろんだよ」と返ってきたことも印象的。
夜の祈り(プージャー)は異世界
夜のガンジス川は、異世界だった。
30分ほど繰り広げられるプージャー。
その後の街中は、まるで悪夢のような時間。
そこにも必死になって生きる子供たちの姿
感動しながら夜の儀式を見ていると、 何度も子どもたちに囲まれ、足を握りしめられる。
泣きそうな顔で、言葉もなく繰り返される「請求」。
心がくじけそうになりながらも、自分を守るために、そっと離れる。
そんな私とは裏腹に、 街中では他人にお金を渡す人々の姿もよく目にした。
日本で“ホームレス”と聞くと、
「働くことから逃げた人」「社会から逸れた人」というイメージを持たれがちだ。
“努力もしないのにお金をもらうなんて”と思う人も少なくない。
日本では、ホームレスを見かけても何度も施しをする人は少ないけれど、
ここではそれが当たり前のように行われている。
彼らは、生まれた時点である程度“人生が決まっていた”人たち。
だからこそ、多くの人が「他人の境遇に対して自分ができること」を
自然と受け止めているように思う。
その根底には、カーストのような社会構造や、
それを前提にした価値観があるのかもしれない。